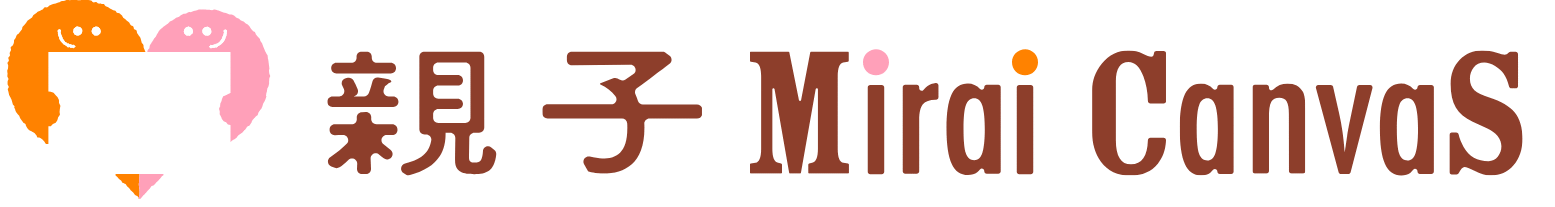目次
第1章|なぜ8月は「防災のチャンス」なのか?
8月は、実は一年で最も自然災害に備えるべき月のひとつです。
理由は以下の通りです。
- 台風シーズン真っ只中:8月から9月は、日本列島に台風が接近・上陸しやすい季節です。
- 集中豪雨や河川氾濫のリスク:夏の終わりは大気が不安定になり、ゲリラ豪雨も多発します。
- 子どもが夏休み中で時間が取りやすい:家族でゆっくりと防災の学びや備えができるタイミングです。
この時期に防災の準備を整えておけば、9月1日の「防災の日」を迎える頃には、家族の備えが万全になります。

ミラキャン
私は東日本大震災の際は青森で生活をしていました。その時は水道も電気も止まり、食料もなく大変怖かった思い出が残っています。そういう経験があるから、防災意識は自然と高まり、防災リュックを2個常備しています。
第2章|親子でできる「楽しい防災体験」
防災と聞くと堅苦しく感じますが、親子で取り組むなら“遊び”の感覚にするのがポイントです。ここでは家でも外でもできる防災体験の例を紹介します。
1. 家の中でできる停電・断水体験
- 夜にブレーカーを落として、ランタンや懐中電灯だけで過ごす
- 水道を止めて、備蓄水や非常食で食事をしてみる
「いざ」という時に子どもが慌てないための訓練になります。
2. 非常食の試食会
- アルファ米や缶詰、レトルトカレーなどを実際に食べる。
- お皿やカトラリーを使わずに食べられる工夫をしてみる
夏休みの自由研究としてレポートにまとめれば、学校提出も可能です。 - 賞味期限が近く、ストックする非常食を入れ替える際は試食会に最適ですね。
3. 避難経路ウォーキング
- 自宅から一番近い避難所まで親子で歩いてみる
- 避難ルートや危険箇所を通りすがりのときにお子さんに伝える

ミラキャン
子どもたちは“ごっこ遊び”が大好き。防災も遊び感覚に変えると、楽しく学べて記憶にも残ります。
第3章|防災とチャリティを組み合わせるアイデア
防災活動は、地域や社会への貢献と組み合わせることで、学びも喜びも倍増します。親子でできる簡単なチャリティ活動の例を挙げます。
- 不要な毛布やタオルの寄付
自宅に眠っている防災用品や毛布を地域の避難所・福祉施設に寄付する。 - 防災ポスター作り
学校で案内があるような絵画コンクールに提出するのもいいですね。
単なる募金よりも、「体験型の寄付」は子どもたちが“自分も誰かを助けられるんだ”と実感できる貴重な経験になります。
そして、与えるものは与えられるという言葉も体験することになるでしょう。
第4章|今すぐ始められる防災×チャリティの第一歩
大がかりな準備は必要ありません。まずは家でできることから始めましょう。
- 非常用持ち出し袋の確認
家にあるものを一度並べて写真に撮り、普段はどこに置いてあるかを家族で共有。 - 地域の防災訓練やボランティアに参加
夏休み中の体験は、親子の絆を深めるきっかけにもなります。 - 100均で防災グッズをお買い物
今では100均でも防災グッズを販売しています。一緒に買い物に行って、使い方や意味などをお子さんと共有するチャンスですね。

ミラキャン
小さな一歩でも、積み重ねると家族も地域も強くなります。チャリティは“余裕のある人だけ”のものじゃなく、誰でも参加できるんです。
第5章|おわりに|備えと優しさが、未来を守る
防災は、ただ災害に備えるためだけではなく、
- 家族の絆を深める
- 社会に優しさを循環させる
- 子どもの心を成長させる
という“未来への投資”でもあります。
8月の防災月間に、ぜひ親子で取り組んでみてください。きっと夏休みの特別な思い出にもなります。
それでは最後まで読んでいただきましてありがとうございました!