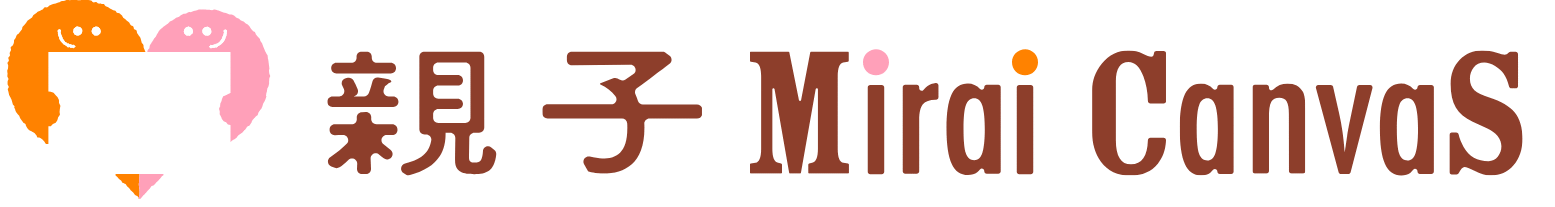はじめに|子どもの情緒は「親の心」から始まる
子どもは、親の表情や声色、態度から多くのことを学んでいます。
最近注目されているのが「情動学習」です。情動学習とは、感情を理解し、コントロールし、他人の感情に共感できる力を育む学びのこと。
学力では測れない「非認知能力」にも直結します。
親が感情的に余裕を持てないと、子どもも不安定になりやすいもの。
だからこそ、親自身のメンタルケアと、家庭での情動学習がこれからの子育てに欠かせません。

仕事や生活に追われると、ついつい子どもにイライラしてしまうことありますよね。まずは親の心に余裕を作ることが、何よりの教育だと感じています。
第1章|情動学習とは?なぜ今注目されるのか
情動学習(Emotional Learning)は、単なる「感情教育」にとどまらず、子どもが自分の心を理解し、相手に共感し、感情を適切に扱える力を育てる学びです。
従来の教育では、計算や暗記など「目に見える学力=認知能力」が重視されてきましたが、社会の変化により、心の土台である非認知能力の重要性が高まっています。
1. 情動学習で育つ3つの力
- 感情認識力(Emotional Awareness)
- 自分の感情や、他人の表情・声色から相手の気持ちに気づく力
- 例:「友達が泣いているから悲しいのかな」「自分は今、怒っているんだ」
- この力があると、衝動的な行動やケンカが減りやすくなります。
- 感情コントロール力(Emotional Regulation)
- 湧き上がった感情を落ち着かせたり、適切に表現する力
- 例:叩きたくなるほど怒ったときに深呼吸する/「悲しい」と言葉にする
- 社会生活の中でストレスに負けない力につながります。
- 共感力(Empathy)
- 他人の感情を理解し、寄り添うことができる力
- 例:友達が失敗して落ち込んでいるときに「大丈夫?」と声をかけられる
- 将来の人間関係やチームワークに直結する大切な力です。
2. なぜ今、情動学習が求められるのか
- 社会の変化による「心のスキル」の必要性
- AIの普及で、単純な知識や暗記の価値は低下
- 将来は「人間ならではの感情理解・共感力」が強みになる時代
- 子どものメンタル不調・ストレス増加
- 文科省の調査でも、小中学生の不登校や気分の落ち込みは年々増加傾向
- 情動学習は、子どもがストレスを自分で整理する術として効果的
- 非認知能力=成功や幸福に直結
- スタンフォード大学の研究でも、非認知能力が高い子は、学業や将来の職業生活でも安定しやすいと報告
- つまり、情動学習は「学力以上に、人生の土台」となる教育です。
3. 家庭でも学校でも導入され始めている
最近では、幼稚園・保育園や小学校で「SEL(Social Emotional Learning)」として情動学習プログラムを導入する動きが広がっています。
海外では、授業の中で以下のような取り組みが行われています。
- 朝の会で「今の気持ち」を色カードで表す
- ケンカや失敗の体験をグループで話し合い、感情を共有する
- 呼吸法や簡単なマインドフルネスで感情を整える時間を作る
こうした取り組みは、家庭でも簡単に応用可能です。

私も、自分の幼少期を振り返ると『泣くな』『我慢しろ』と言われることが多かったです。でも、感情に名前をつけてくれる大人がいたら、もっと楽に生きられたかもしれません。子どもに感情の言葉を渡すことは、未来への最高のギフトだと思います。
第2章|親子でできる情動学習の実践法
情動学習は、特別な教材や高価なスクールに通わなくても、家庭の毎日の会話や遊びの中で育てられる力です。
ここでは、親子で取り入れやすい実践法をステップごとに紹介します。
1. 感情に「名前」をつける習慣
子どもは、感情を感じていても言葉で表現できないことが多く、
怒りや悲しみがそのまま泣き叫びや暴れに変わることがあります。
そこで有効なのが、感情のラベリング(Labeling Emotion)です。
- 例:「悔しいんだね」「悲しかったんだね」「楽しくて笑ってるんだね」
- 親が代わりに言語化してあげると、子どもは“自分の気持ちを整理する”第一歩を踏み出せます。
心理学では、感情に名前をつけるだけでも脳の扁桃体が落ち着くことが知られています。
つまり、泣いている子に「泣き止みなさい」と言うより、感情を言葉にするほうが落ち着きやすいのです。
2. 1日1回の「感情シェアタイム」
情動学習には、安心して感情を話せる時間が必要です。
おすすめは夕食時や寝る前に「今日の気持ち」を親子で話す習慣です。
- 子ども:「今日、体育で転んで恥ずかしかった…」
- 親:「そっか、恥ずかしかったんだね。痛くなかった?」
- 子ども:「ちょっと痛かったけど、友達が笑ってて…」
- 親:「笑われるとつらいよね。でも、よく頑張ったね」
このやり取りだけで、子どもは安心・共感・感情整理を同時に体験できます。
最初は短くても構いません。「今日はどんな気持ちだった?」と一言聞くだけでも効果があります。
3. 感情を表現する遊びを取り入れる
言葉でうまく表現できない小さな子どもには、遊びの中で感情を表現させることが有効です。
- 絵で気持ちを描く:「今日の気持ちを色で描いてみよう」
→ 怒りは赤、楽しいは黄色など、色で感情を可視化 - お人形やぬいぐるみで気持ちを代弁
→ 「クマさん、今日は悲しいの?」など、投影を通して感情を整理 - 感情カードを作る
→ 嬉しい・悲しい・怒り・びっくりなどの顔イラストを使い、選ぶだけで気持ちを表現
心理学的にも、非言語的な表現方法を持つと感情処理能力が高まるといわれています。
4. 親が「見本」を見せる
情動学習は、言葉だけでなく、親自身の態度から子どもが学ぶ部分が大きいです。
以下のような見本行動が効果的です。
- イライラしたら深呼吸する姿を見せる
- 「ちょっと疲れたから、5分だけ休むね」と気持ちを言葉にする
- 喜びや感謝を積極的に口に出す
感情をため込まず、言葉で表現しながら整える姿を見せるだけで、子どもも自然とマネします。
5. ゲーム感覚で続ける工夫
情動学習は毎日の積み重ねが大切ですが、最初は「遊び感覚」で取り入れると続けやすくなります。
- 感情ビンゴ:「今日の気持ちはどれ?」シールを貼るだけ
- 感情ジェスチャーゲーム:親子で「嬉しい顔」「悲しい顔」を当てる
- ストーリーテリング:「今日の気持ちを一言で日記に書く」
楽しい体験に変えることで、子どもが自ら感情を表現する習慣が身につきます。

夜寝る前に『今日の気持ちベスト3』を言い合う時間を作ってみるといいかも。
最初は照れていた子どもも、今では『今日は嬉しいが1位!』と笑顔で話してくれるようになります。
親子の会話が増えるだけでなく、親自身の心も整理される時間になっています。
第3章|親のメンタルケアが子どもに与える影響
子どもの情緒は、親の心の状態を鏡のように映すといわれています。
親が焦りや疲れ、不安を抱えていると、子どもは敏感に察知して不安定になりやすくなります。
逆に、親が落ち着いて笑顔でいられるだけで、子どもは安心感に包まれ、感情を安定させやすくなります。
1. 親の感情が子どもに伝染する理由
心理学では、これを「情動感染(Emotional Contagion)」と呼びます。
赤ちゃんが泣いている母親を見ると泣き出すのも、親の表情や声色から感情が伝わるからです。
- 親がイライラしている → 子どもも落ち着かず、些細なことで泣く・怒る
- 親が落ち着いている → 子どもも安心して遊びに集中できる
つまり、親の心の安定は、子どもの情緒安定に直結する「無言の教育」なのです。
2. 親がメンタルを整えるメリット
親が心を整えることは、次のような効果をもたらします。
- 子どもに安心感を与える
- 親が笑顔でいると「大丈夫」というメッセージになり、情緒の土台が安定する
- 感情的なしつけが減る
- 親の余裕が増えることで、怒鳴る・否定する回数が減り、子どもとの関係が良好に
- 共感と対話の時間が増える
- メンタルに余裕があると、子どもの話をゆっくり聞く余白が生まれる
- 親自身の幸福感が上がる
- 家庭の雰囲気も明るくなり、親子ともに「居心地のよい家」になる
3. 親のメンタルケアの実践法
子どもの情緒を守るには、まず親が心を整えることが第一歩です。
忙しい日常でも取り入れやすい方法をいくつか紹介します。
- 1日5分のマイタイムを確保する
- コーヒーを飲む、ベランダで深呼吸するなど、短時間でも「自分だけの時間」をつくる
- 感情を言葉にして手放す
- ノートに「今日イライラしたこと」を書き出し、客観的に見るだけで感情は軽くなる
- 軽い運動や散歩でリセット
- 運動はセロトニンを増やし、気分を安定させる効果がある
- 「助けを借りる」勇気を持つ
- 実家や一時預かり、ベビーシッターなどを利用し、親が休む時間を確保する
- 感謝習慣でポジティブを増やす
- 寝る前に「今日のよかったこと」を3つ書くだけでも、幸福感が高まりやすい
4. 完璧な親でなくていい
親のメンタルケアで大切なのは、「無理をしないこと」です。
完璧に育児も家事もこなす必要はありません。
むしろ、疲れたときは「今日は手抜き!」と割り切ったほうが、家庭全体の幸福度は上がります。
子どもにとって必要なのは、
「いつもニコニコ完璧なお母さん・お父さん」ではなく、
気持ちを整えて一緒に笑える親です。

子どもに『ママ、なんか怒ってる?』と言われたことがありますか?
そのとき、自分の疲れやストレスがそのまま伝わっていたんだと思います。
今は意識的に5分だけでも休むようにして、笑顔で『おかえり』と言える自分を作ることを大事にしています。
第4章|今日からできる親子の情動学習習慣
情動学習は、特別な時間を作らなくても、日常の小さな行動の積み重ねで育まれます。
ここでは、今日からできる具体的な習慣を紹介します。
1. 朝の「気持ちのあいさつ」をする
一日のスタートに、いつもの「おはよう」に感情をひと言添えるだけでも効果的です。
- 例:「おはよう、今日はワクワクしてるよ」「昨日の絵、嬉しかったな」
- ポイント:感情を表に出すことで、子どもも「自分の気持ちを話していいんだ」と安心する
心理的効果
ポジティブな感情表現は、親子の一日の気分を明るくスタートさせます。
2. 「感情シェアタイム」を1分だけでも毎日
夕食や寝る前に、親子で今日の気持ちを振り返る時間を作りましょう。
- 例:「今日の嬉しかったこと」「今日のちょっと嫌だったこと」を1つずつ話す
- 子どもが話せないときは「顔カード」「感情カード」を見せて選ばせてもOK
ポイント
- 無理に話させないこと
- 親も正直に話すことが信頼関係につながる
3. 感情を「見える化」する遊びを取り入れる
子どもは、言葉だけでは感情を整理できないことがあります。
絵・色・ジェスチャーを活用すると表現がスムーズです。
- 「今日の気持ちを色で塗ろう」:青=さみしい、赤=怒り、黄色=楽しい
- 感情ジェスチャーゲーム:「今の顔はどんな気持ち?」を親子で当てる
- ぬいぐるみを使って「うさぎさんは今どんな気持ち?」と投影させる
心理的効果
非言語的表現が増えることで、子どもは感情を外に出しやすくなり、心が落ち着く。
4. 「ありがとう」と「よかった」を増やす
情動学習の基本は、感情に寄り添うことと、ポジティブな感情を意識することです。
- 寝る前に「今日のありがとう」を3つ言う
- 何かできたら「よかったね」「頑張ったね」と共感する
- できなかったことより、できたことに注目する
心理的効果
感謝の習慣は、自己肯定感の向上とストレス軽減につながります。
5. 親も「感情を言語化」する
情動学習は、親が見本を見せることから始まります。
- 「今はちょっと疲れているから、5分だけ休むね」
- 「さっきイライラしたけど、もう落ち着いたよ」
ポイント
- 子どもに怒鳴る前に深呼吸し、言葉で気持ちを伝える
- 「怒ってはいけない」ではなく、「怒りを整える」を意識する
6. 習慣化のコツ
- 無理せず、1分から始める
- 続けるために「寝る前」「夕食後」など、時間を固定する
- 楽しさを優先し、叱る時間にはしない

寝る前に『今日のありがとう3つ』を言い合ってみましょう。
最初は照れますが、子どもから『ママ、遊んでくれてありがとう』と言われたとき、胸が熱くなります。
親子で感情を分かち合うだけで、日常がもっと温かくなると実感しています。
まとめ|親子で心を整える時間が未来の宝物に
情動学習は、親子のコミュニケーションの質を上げ、子どもの心を豊かにします。
そして何より、親の心に余裕があることで、子どもは安心して伸びていきます。
親子で感情を分かち合う習慣は、将来「思い出」としても残る最高のギフト。
今日から1分の心の交流を、ぜひ始めてみませんか?
これは、子どもが大人になったらできない教育です。
お子さんが小さいころにだけできる貴重な機会ですし、何よりも、このようなやりとりが、親御さんの心の中に思い出として一生残ります。
こういった宝物をぜひ1つずつお子さんと作っていってくださいね。
それでは最後まで読んでいただきましてありがとうございました!