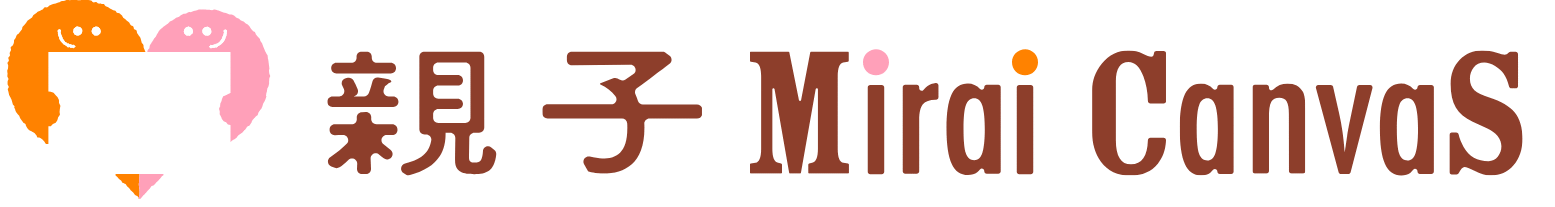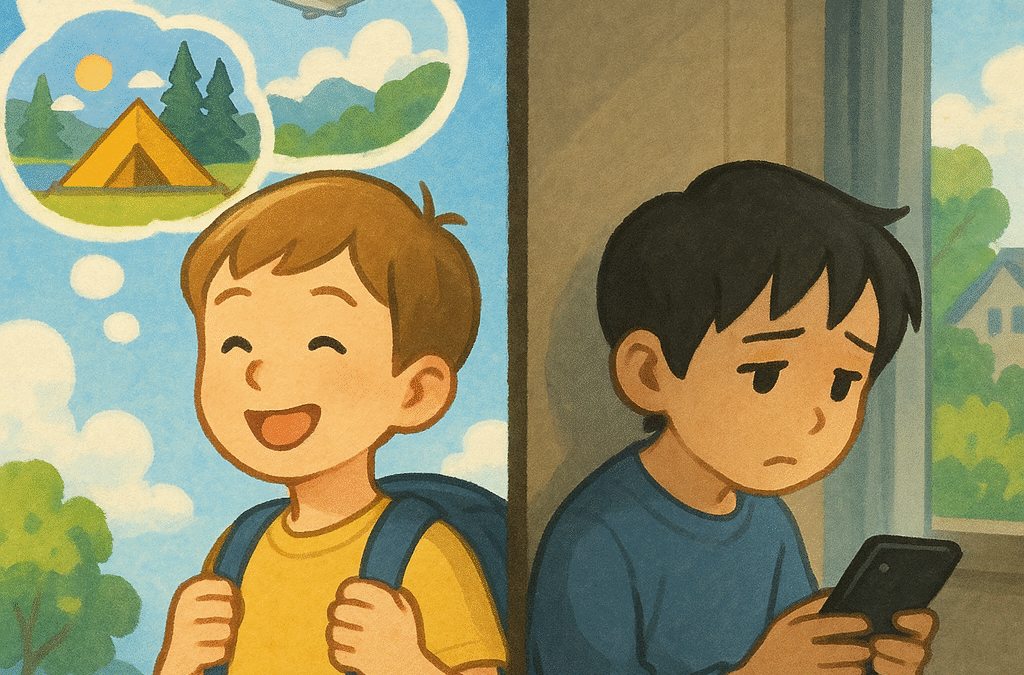はじめに
近年、「体験格差(たいけんかくさ)」という言葉が注目されています。これは、子どもたちが家庭の経済状況や地域の環境によって「学校外での体験機会」に大きな差が出る社会課題です。
実はこのブログを運営する私自身も、かつて経済的に苦しい状況にあり、子ども時代に十分な体験を得ることができませんでした。
親や親戚からも「お母さんがひとりで育ててくれたんだから、お前は親を食わせるために地元で公務員になれ」としか言われてこず、自分の選択肢は存在しないという錯覚をしておりました。
さらに大人になってからは、実際に公務員になったものの、やはり自分というアイデンティティは発揮できず、自分にとって面白みのない業務を淡々とこなし、生きている実感は特にありませんでした。
特に覚えていることは、お父さんがいなかったため、お父さん世代の方、つまり、大人の男の人と話したことがほとんどなく、異常に怖かったことを覚えてます。
新卒1年目、上司にはたくさんの大人の男性がいて、かなり委縮していたことを覚えています。
どれだけ子どもの頃に、体験を積むか、社会性を養うかで、今後の人生に大きく左右するかを身をもって体験してきました。
だからこそ私は、「体験」や「社会」、「正しい知識」にアクセスできない子どもたちを一人でも減らしたい。そんな思いでこの記事を書いています。
この記事では、体験格差の定義や背景、具体例とその影響、そして私たちができる支援のかたちまでを丁寧に解説していきます。
体験格差とは?
「体験格差」とは、子どもたちが学校外で得られる体験機会に、生まれ育った環境によって格差が生じている状態を指します。旅行、習い事、博物館や劇場での文化体験、自然とのふれあい、スポーツなど、その種類は多岐にわたります。
例えば以下のような体験が、すべての子どもにとって「当たり前」ではありません:
- 家族旅行で他県や他国に行く
- 博物館や美術館を訪れる
- 家族以外の人たちとのコミュニケーション
- スポーツや音楽などの習い事に通う
- 親と一緒に料理やキャンプなどをする
一部の家庭にとっては当たり前でも、経済的・地理的理由によりその機会が得られない子どもも数多く存在します。
特に私は一人っ子で、家族以外の人たちとのコミュニケーションがなかったため、人見知りで引っ込み思案な部分もありました。
子どもに与える影響
文部科学省の調査によると、体験活動には以下のような教育的意義があります【出典:文部科学省】:
- 現実の世界や生活などへの興味・関心、意欲の向上
- 問題発見や問題解決能力の育成
- 思考や理解の基盤づくり
- 教科等の「知」の総合化と実践化
- 自己との出会いと成就感や自尊感情の獲得
- 社会性や共に生きる力の育成
- 豊かな人間性や価値観の形成
- 基礎的な体力や心身の健康の保持増進
特に、幼少期に多様な体験をした子どもほど、将来の自尊感情が高まり、意欲的・積極的に生きる傾向が見られることが明らかになっています。
なぜ体験格差が生まれるのか?主な原因と背景
1. 経済的格差
旅行や習い事、イベント参加にはどうしても費用がかかります。シングルマザー・ファザー世帯や、非正規雇用の多い家庭では、これらの体験に投資できる余裕がありません。そのため、いわゆる「世間知らず」という状況に陥ります。うちの家庭がまさにそうでした。
2. 地域格差
都市部に比べ、地方や中山間地域では体験の選択肢が限られています。逆に、自然体験はできても文化施設や多様な交流の機会が少ないケースもあります。
3. 情報格差
「こんな体験ができるらしい」「無料で参加できるイベントがある」といった情報が届いていないことも問題です。情報へのアクセスが、体験機会の差を生むこともあります。うちの家庭も、テレビしか見ないため、イベントなどに行くということは皆無でした。当時は新聞も取っておらず、情報源はテレビだけで偏りのあるものでした。
4. コロナ禍による影響
現在では薄れてきておりますが、外出制限・イベント中止・学校行事の縮小などで、体験機会が大きく制限されました。この影響は家庭によって差があり、ICT環境の整備が遅れていた家庭では、教育・体験の両面で深刻な影響が出ています。
体験格差の“連鎖”とは?
体験格差の深刻な問題は「親の体験不足が次の世代にも引き継がれること」です。体験の価値を知らないまま大人になった親は、子どもにも積極的に体験させるという発想に至らないことがあります。
この連鎖を断ち切るには、社会全体で「体験の価値」を再認識し、特に支援を必要とする家庭に対して具体的なサポートが求められます。
また、親御さんの過度なお子さんへの期待、なども体験格差を生みます。
「うちの子は医者・弁護士になってもらいたいから」
「私が叶えられなかった夢を叶えてほしいから」
これは、ベクトルが子どもに向いているのではなく、親御さんの夢を叶えるために子どもに「やらせている」ことから引き起こされます。
私自身も「公務員になるため」に育てられました。
それでは子どもは幸せにはなりません。敷かれたレールを歩くことに、人生のおもしろさなんてありません。
親子Mirai Canvasができること 〜体験格差をなくすために〜
夏休みの作文、絵日記にかける思い出をプレゼントしよう!
そういうテーマでこの団体を立ち上げました。
もちろん夏だけでなく、四季折々、さまざまなイベントをプレゼントし、親子にとってかけがえのない思い出という宝物を贈ります。
そのためにも、ぜひみなさまのお力を1%でもいいので貸してください。
具体的には以下の内容です。
● 自分の時間を寄付する(ボランティア)
イベントスタッフとして、お手を貸してください。
お礼として、ホームページにてご紹介をさせていただきます。
●知識・情報を寄付する(ボランティア)
ご自身のご職業・業界の知識をぜひセミナー・講師・ワークショップ・記事・さまざまな形で提供いただけませんか?
お礼として、ホームページにてご紹介をさせていただきます。
● 情報を広める
周りのご家族に積極的にお伝えください。SNSやブログでの発信も立派なアクションです。
● 金銭の寄付
忙しくてどうしても、、、でも思いはある!という方はぜひとも金銭的なご寄付をお願いします。
寄付についてはこちらをご覧ください。
● 企業の方へ
CSR活動の一環として、そしてスポンサーとしてイベントの費用を広告宣伝費として支出いただけませんか?
御社のサービス・商品を活用したイベントを企画し、体験として親子に提供するようなことも可能です。
我々のイベント企画チームが目一杯頭を働かせて、アイデアを出し、素敵なイベントを作ります。
ホームページにて活動報告とともに、御社のPRもさせていただきます。
まとめ
体験格差は、貧困や地域差といった目に見える問題だけでなく、「知らない」「関わらない」ことからも生まれます。
私自身の経験からも、体験は“生きる力”の土台になることを強く実感しています。
自分にとって当たり前のことは、意外と気づきにくいものです。
まずは、体験格差を知っていただき、そして1%でもいいので、行動に移していただけたらとてもうれしいです。
一人でも多くの子どもに「心が動く体験」を届けたい。社会全体でその価値を再認識し、できることから動いていくことが今、求められています。