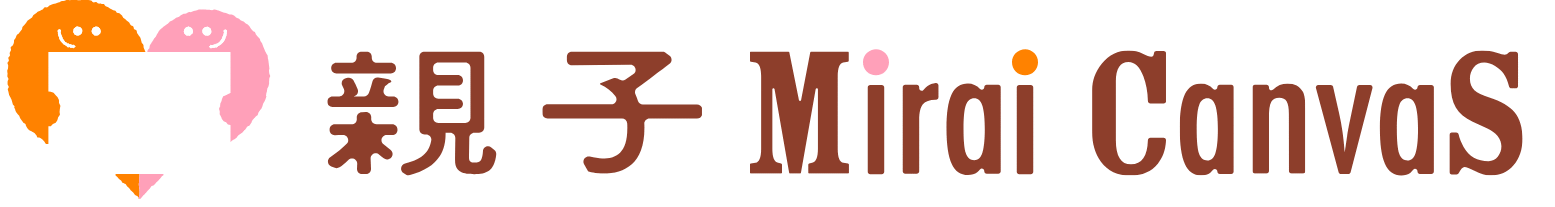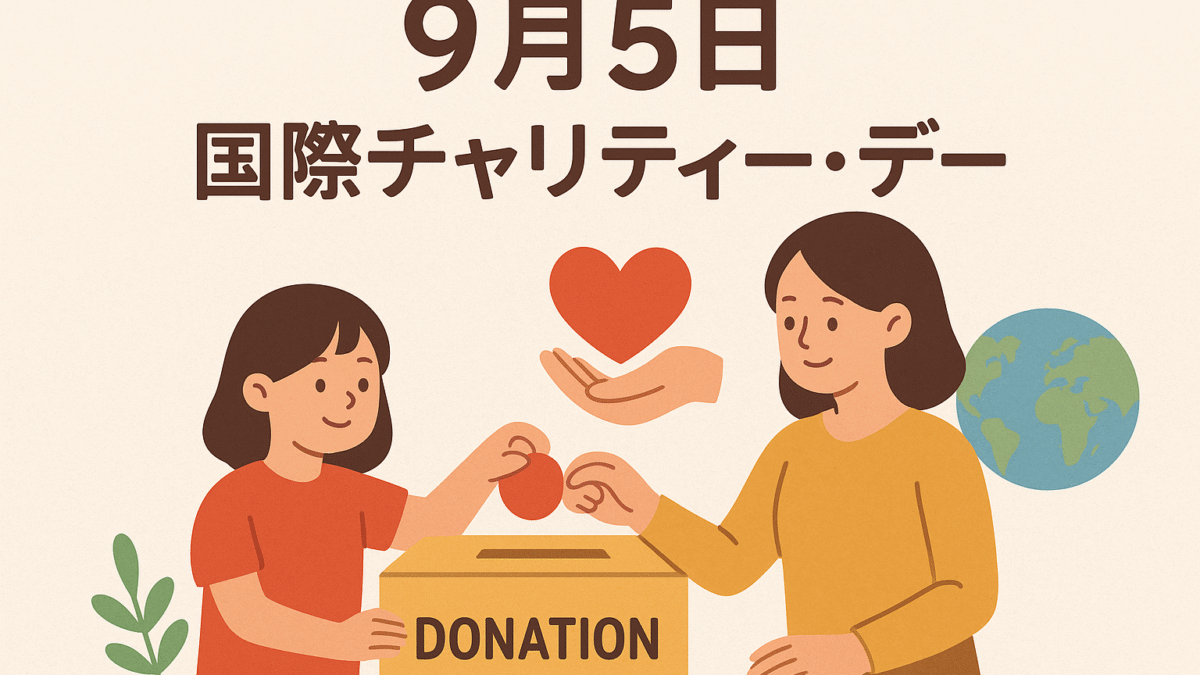毎年9月5日は「国際チャリティー・デー」です。これは国連が2012年に制定した記念日で、世界中の人々に「慈善活動の大切さ」を広め、社会的な連帯や思いやりを促すことを目的としています。
この日は、マザー・テレサの命日であることから選ばれました。
国際チャリティー・デーを知ることは、自分にできる社会貢献の形を考える大切な機会になります。
ここでは、その意味や活動例、親子でできる取り組みについて解説します。
国際チャリティー・デーが生まれた背景
国際チャリティー・デーは2012年に国連総会で採択され、翌年から正式に実施されました。
この日付が選ばれたのは、1997年9月5日に亡くなったマザー・テレサの功績を称えるためです。
彼女はインド・カルカッタで「死を待つ人の家」を設立し、貧困や病気で苦しむ人々に寄り添いました。
その姿勢は「無償の愛」の象徴として世界中に影響を与えました。
また、この日が国際デーとなった背景には、世界の不平等や格差がますます広がっているという現状があります。
国連の報告によれば、世界人口の約9%は極度の貧困下で暮らしており、子どもたちの教育や医療へのアクセスも不十分な地域が存在します。
こうした状況を改善するには、政府や企業の取り組みだけでなく、個人の行動が不可欠です。
国際チャリティー・デーは「一人ひとりの力が社会を変える」という理念を広めるためのきっかけとして制定されたのです。

私はマザー・テレサの言葉「私たちがしていることはほんの一滴にすぎないと感じます。でも、その一滴がなければ海は寂しくなるのです」という言葉が好きです。小さな寄付や行動が社会の大きな変化につながるというメッセージは、自分の活動の励みになっています。
国際チャリティー・デーにできること
「チャリティー」というと、多額の寄付や大規模な活動を思い浮かべる方も多いかもしれません。
しかし実際には、身近で小さな行動も立派なチャリティーの一歩です。
例えば次のような取り組みがあります。
- 寄付(お金・物品)
・ワンコイン(500円)を寄付
・読まなくなった絵本や子ども服を寄付団体へ送る - ボランティア参加
・地域の子ども食堂や高齢者サポートの活動に参加
・災害時の物資仕分けや募金活動の手伝い - チャリティーイベントの応援
・チャリティーマラソンやバザーに参加
・SNSで支援活動をシェアして拡散する - 日常生活での選択
・フェアトレード商品を購入する
・エシカル消費(環境や人にやさしい商品)を選ぶ
こうした行動は、自分にとって負担が少なくても、社会にとっては確実な「プラスの循環」を生み出します。

私はチャリティーを「特別なイベント」ではなく「日常の延長」として捉えるようにしています。コンビニの募金箱に小銭を入れることも立派な社会貢献。そう考えると続けやすく、結果的に大きな力になると感じます。
親子でチャリティーを体験する
チャリティーを「親子の体験」として取り入れると、子どもにとっては学びの場となり、大人にとっても社会貢献を家族で共有できる機会になります。
具体的な取り組み例を挙げると、次のようなものがあります。
- 家の中の不要品を整理して寄付する
子どもと一緒に衣類やおもちゃを選び、まだ使えるものを必要とする人に届ける。
モノを「捨てる」ではなく「生かす」体験になります。 - 募金体験
小銭を子どもに渡し、募金箱へ入れてもらう。
お金には「自分のために使う」だけでなく「人を助ける使い方」があることを体験的に学べます。 - 親子でボランティア参加
地域の清掃活動やチャリティーイベントに一緒に参加する。
子どもは社会の一員として行動する喜びを知り、大人も子どもの成長を実感できます。 - 寄付先を一緒に選ぶ
「動物を守りたい」「困っている子どもを助けたい」など、子どもの関心に合わせて支援先を探す。
自分で選んだことが大きなモチベーションになります。
こうした取り組みは、単なる社会貢献ではなく「親子での思い出作り」にもなります。
将来、子どもが「小さい頃に一緒に寄付をしたな」と思い出せば、その価値はお金以上の宝物になるでしょう。

私は子どもの頃に「誰かのために行動する」体験をほとんどしませんでした。だからこそ、大人になった今、親子で一緒にチャリティーを体験することに価値を感じています。支援活動は「与える側」だけでなく「受け取る側」にも学びがあると実感しています。
まとめ
国際チャリティー・デーは「特別な人が行う立派な活動の日」ではなく、誰もが「できることから始める日」です。
大切なのは「小さくても継続できる行動」を意識することです。
・500円の募金が子どものごはん代になる
・古着1枚が寒さに苦しむ人の命を守る
・イベント参加の一歩が地域の活性化につながる
私たち一人ひとりの行動が、社会を少しずつ良い方向へ変えていきます。
そして親子で取り組むことで、その循環は次の世代へと受け継がれていきます。
国際チャリティー・デーをきっかけに、ぜひ「自分にできること」を考え、行動に移してみてください。
その一歩が誰かの笑顔につながり、やがて社会全体を明るくする力になります。

私は「寄付=未来への投資」だと考えています。お金や時間を使うことで子どもたちの笑顔や可能性を広げ、それが社会の希望へとつながる。だから9月5日を単なる記念日ではなく、行動を起こすチャンスにしていきたいと思います。
それでは最後まで読んでいただきましてありがとうございました!