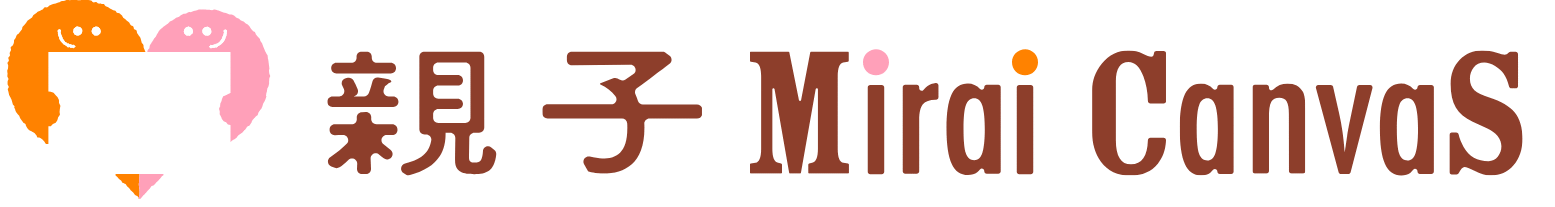はじめに|子どもの心は想像以上に繊細です
最近、子どもの不登校やうつ、学校でのストレスによる体調不良が増えています。
文部科学省の調査でも、不登校の小中高生は過去最多の30万人超。
背景には、いじめや学業ストレス、家庭環境など、さまざまな要因があります。
しかし、日本の学校はまだ「心の予防ケア」が弱く、問題が表面化してからの対応になりがちです。
だからこそ、家庭でできる小さな習慣や選択肢が、子どものメンタルヘルスを守る大きな力になります。
第1章|子どもの心が疲れるサインに気づく
子どものメンタルヘルスは、目に見えにくいものです。
大人が思う以上に、子どもは周囲の空気を敏感に感じ取り、我慢しがちです。
だからこそ、日常の小さな変化に気づくことが、家庭でできる最初の予防策です。
1. よくある心のSOSサイン
- 朝になると体調不良を訴える
- 頭痛、腹痛、吐き気など、病院に行っても原因が見つからないことも多い
- 体よりも心が疲れているサインかもしれません
- 感情の波が激しくなる
- 些細なことで泣く、怒る、黙り込む
- 本人も理由がわからないことが多く、自己嫌悪につながる場合もあります
- 好きだったことへの興味を失う
- ゲームや遊び、好きな話題にも反応が薄くなる
- 楽しいことすらエネルギーが必要で、心が休みを求めている状態です
- 生活リズムが乱れる
- 夜寝つけない、朝起きられない、食欲が落ちる
- 体内時計の乱れもメンタル不調のサインです
2. 気づくための家庭での工夫
- 「毎日の小さなチェック」を習慣にする
「今日の気分は0〜5でどれくらい?」と数字で聞くと、子どもも答えやすいです
例)0=とてもつらい、5=とても楽しい - 変化をメモして見える化
カレンダーやノートに、気分や体調の変化を記録
連続で低めの数字が続いたら、早めに休ませるサイン - 言葉にならない気持ちも受け止める
話したがらないときは無理に聞かず、「そばにいるよ」とだけ伝える
安心できる空気が、子どもが自分から話し始めるきっかけになります

私も子どものころ、学校に行きたくない理由をうまく言えなかったことがあります。当時は「絶対に学校に行け」という厳しい母親の言葉があってそれが当たり前みたいな風潮があったのかと思いますが、当時と今では状況が違います。
“どうしたの?”よりも、“今日は家にいてもいいよ”と言われたら、どれだけ救われただろうと思います。
第2章|家庭でできる“心の守り方”3つの習慣
子どもの心を守る一番の力は、家庭での日常にあります。
特別な道具や資格は必要ありません。
毎日少しずつの積み重ねで、子どもは「ここにいて安心だ」と感じられるようになります。
- やり方
朝や夜に「今日の気分は0〜5でどれくらい?」と簡単に聞く
0=とてもつらい、5=とても楽しい - ポイント
・数字で答えるだけなので、子どもが話しやすい
・低い数字が続いたら「無理をしない」サインとして受け止める - 例
「今日は2なんだね。じゃあ、今夜はゆっくり好きなことしようか」
- やり方
家の中や外に、子どもが落ち着ける場所を一緒に決める
例)子ども部屋のベッドの隅、祖父母の家、近所の図書館、子ども食堂 - ポイント
・「学校に行かないといけない」という思い込みを和らげる
・物理的な避難先があるだけで、心に余裕が生まれる - 例
「明日はしんどかったら、おばあちゃんの家で休もうね」
- やり方
無理に話さなくてもよいので、同じ空間でのんびり過ごす
例)一緒にお茶を飲む、横で本を読む、ペットと遊ぶ - ポイント
・「そばにいる安心感」が最大のメンタルケア
・干渉せず、子どもが話したくなったら耳を傾ける - 例
「今日は何もせず、ソファでごろごろしようか」
第3章|家庭でできる小さなステップで心を回復させる
子どもの心が疲れてしまったときは、無理に学校に戻そうとするよりも、家庭で小さな“回復の階段”を一段ずつ上がることが大切です。
- やり方
朝に体調や気分がすぐれない様子なら、無理に登校させない
「今日は休んでも大丈夫」と一言かける - ポイント
・登校しないことを責めない
・安心感が次の一歩につながる - 例
「今日は2の気分か…じゃあ今日は家で休もうか」
- やり方
家でだらだら過ごす→軽い運動や散歩に誘う
例)ベランダで日向ぼっこ、犬の散歩、近所を5分だけ歩く - ポイント
・外の空気を吸うだけでもリフレッシュになる
・無理に長時間出かける必要はない - 例
「今日はお日さま出てるね。5分だけ外の空気吸いに行こうか」
- やり方
ゲーム、絵を描く、工作、料理など、子どもが夢中になれることを一緒にやる - ポイント
・「楽しい」と思える体験が自己肯定感を回復させる
・親は口出しせず、見守り役に徹する - 例
「昨日の続きの絵を見せてくれる?今日は私も隣で描いてみようかな」
- やり方
学校復帰を急がず、家の外で安心できる場所に短時間出てみる
例)図書館、スーパー、祖父母の家、子ども食堂 - ポイント
・「外に出られた」経験が自信になる
・いきなり学校ではなく、段階的に外の世界に慣れる - 例
「今日はおばあちゃん家に10分だけ行ってみようか」

逃げ場がないことが一番危険。まずは“休んでいい”と受け止めることで、子どもは少しずつ自分の足で立ち上がれるんだと思います。
第4章|学校以外の学び・居場所を活用しよう
学校がつらいとき、無理に通い続ける必要はありません。
今は「学校以外の学び方」や「安心できる居場所」が増えています。
家庭で選択肢を知っておくだけで、子どもも親も気持ちが軽くなります。
選択肢1|フリースクール
- 概要
不登校の子どもが安心して学べる民間施設。
学習よりも心の回復や自己肯定感を重視しているところが多い。 - メリット
・少人数制で、無理なく通える
・同じ状況の子ども同士が支え合える - 行動ステップ
- 「フリースクール+地域名」で検索
- 無料体験や見学を予約
- 子どもと一緒に行ってみて感触を確かめる
選択肢2|オンラインスクール・ネットの学び
- 概要
自宅で自分のペースで学べる通信制やオンライン学校。
最近はクラスメイトと交流できるオンラインコミュニティも増加。 - メリット
・登校せずに学習のペースを維持できる
・画面越しの交流が社会復帰のステップになる - 行動ステップ
- 「オンラインスクール 不登校」で検索
- 説明会・資料請求で内容を確認
- 短時間の授業から試す
選択肢3|地域の子ども食堂・学習支援の場
- 概要
食事や宿題サポートが受けられる地域の安心拠点。
家でも学校でもない“第3の居場所”として心を支えてくれる。 - メリット
・参加費は無料または低価格
・大人の見守りがあり安心感がある - 行動ステップ
- 「子ども食堂+市区町村名」で検索
- 開催日・対象年齢をチェック
- 初回は親子で一緒に参加してみる

今の時代、学校である理由もなくなってきました。むしろ、無理やり個性を強制され、「みんなと同じ」「平均であることが望ましい」という昔ながらの体制の教育は現代の社会に対応しきれなくなってきています。子どもが学校に合わせるよりも、子どもの個性やあり方にあった居場所を探すことがな一番の成長の助けになります。
第5章|親子Mirai Canvasができること
私たち「親子Mirai Canvas」は、子どもの心を守る家庭と地域をつなぐ取り組みをしています。
親子が安心して笑顔で過ごせる時間を増やすために、次のようなサポートを行っています。
1. 親子で参加できるイベント
- 夏休みの水遊び、秋の収穫体験、冬のクリスマス会など
- 目的は「子どもが笑顔で過ごせる場所」を増やし、体験格差を解消すること
- 親も子も自然体で楽しめるから、心のリフレッシュにつながる
2. 無料・低価格での体験プログラム
- 工作教室、簡単料理体験、農業体験、音楽会など
- 学校以外の場で体験を積むことで、子どもの将来の選択肢・可能性・視野・社会性・自己肯定感を養います
3. 家庭での心のケア相談
- 「子どもが学校に行きたくない…」
- 「どう声をかけたらいいかわからない」
こうした悩みを一人で抱え込まず、気軽に相談できる窓口を設けています。 - コミュニティを形成し、同じ経験をした先輩ママ・パパからアドバイスを受けれるような支え合いをします。
4. 地域の支援情報の橋渡し
- フリースクール、子ども食堂、学習支援など、地域の安心拠点を紹介
- 必要に応じて、実際の参加のきっかけ作りまでサポート
- 行政の取り組み・制度のシェア

子どもの笑顔は、家庭だけじゃなく地域全体で守れると信じています。
“学校に行くか行かないか”にとらわれず、地域のみんなでお子さんの成長を見守りサポートする環境を我々は作っていきます。
まとめ|家庭の安心感が最大のメンタルシールド
子どもの心は、家庭の安心感で守られます。
社会や学校の対応を待つより、家庭でできることを積み重ねることが、子どもの未来のメンタルヘルスを守る一番の近道です。
子どもが学校に行きたくないと言った時には、頭ごなしに言うのではなく、傾聴してみてください。
それを言い出すこともかなり勇気がいることです。
しっかりと受け止めてあげてくださいね。
それでは最後まで読んでいただきましてありがとうございました!