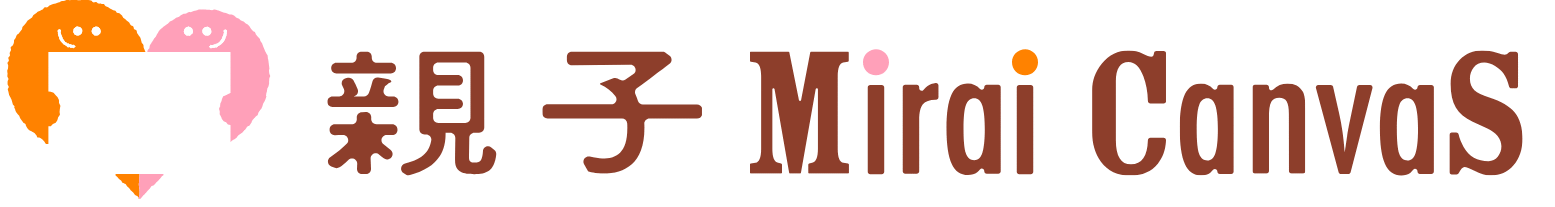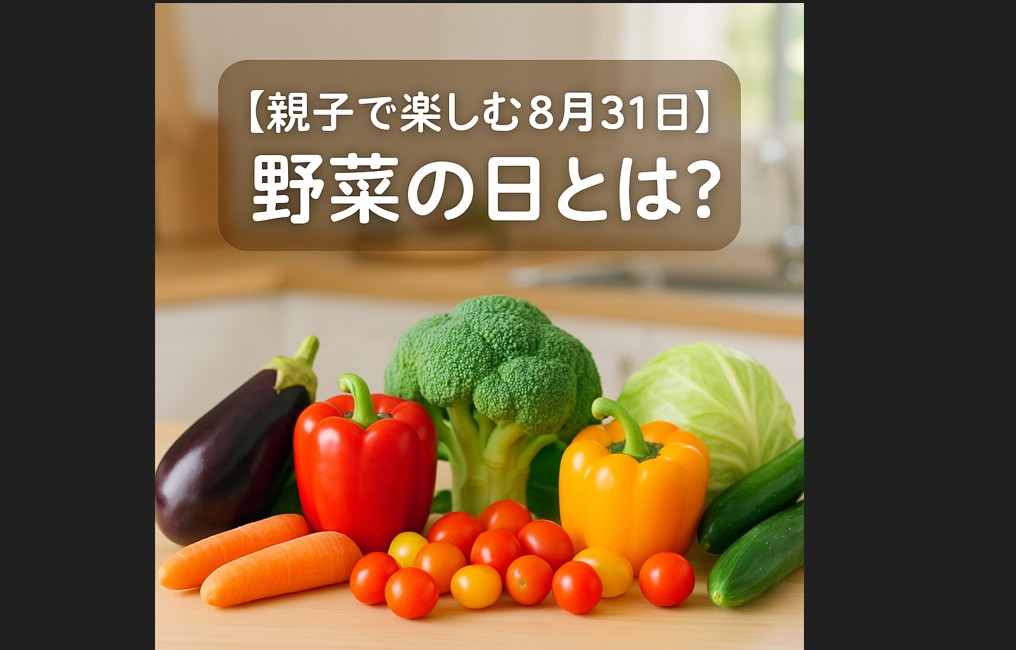はじめに|8月31日は“野菜の日”って知ってた?
夏休みの終わりにやってくる8月31日。
実はこの日は「野菜(ヤサイ)の日」なんです。
「831=やさい」という語呂合わせから、1983年に制定されたこの記念日は、健康的な食生活の大切さを見直す日として広がっています。
家庭でもできる「親子で楽しむ野菜の日」、今年はちょっと特別な思い出にしてみませんか?
第1章|野菜の日の由来と意義を子どもにもわかりやすく伝えよう
8月31日は「831(ヤサイ)」という語呂合わせから、1983年に全国青果物商業協同組合連合会、全国中央卸売市場青果部会、日本青果物商業協同組合連合会の3団体によって制定されました。
当時からすでに懸念されていたのは、現代人の野菜離れ。
特にファストフードや加工食品が増えた時代背景の中で、食卓から「旬の野菜」や「手作りの料理」が減り、子どもの栄養バランスに悪影響を及ぼしていたのです。
そこでこの日をきっかけに、
- 野菜の魅力を再発見すること
- バランスの取れた食事を意識すること
- 旬の野菜を楽しむこと
が、家庭でも大切にされるようになりました。
とくに現代の日本では、小中学生の野菜摂取量が国の推奨量を大きく下回っているというデータも出ており、生活習慣病のリスクを小さいうちから抱えている子どもも少なくありません。
そこで重要なのが、「野菜=体にいい」という単なる知識ではなく、「野菜って楽しい」「おいしい」「きれい」という“感覚”で子どもに伝えることです。
たとえばこんな声かけをしてみましょう:
「にんじんは目を守るヒーローなんだって!」
「トマトの赤は“元気カラー”だね。今日の気分にぴったり!」
言葉を工夫するだけで、子どもたちの野菜への印象がガラリと変わります。

「野菜は残さないでね」と怒ってしまってしまいがちですが、それよりも「この人参、すごい形だね!」と親御さん自身が楽しむ形でいると、お子さんも一緒に楽しくなります。そうすると意外と食べてくれるかもしれませんね。
第2章|親子で「野菜の日」を楽しむ3つのアイデア
野菜の日を単なる「食材の記念日」で終わらせないために、家庭でできる楽しいアクションを3つご紹介します。
1. ベジタブルアートに挑戦!
食材でつくる“アート作品”は、遊び感覚で野菜に触れられる絶好のチャンス。
以下のようなものがおすすめです
- トマトでてんとう虫
- パプリカのカラフル花びら
- ブロッコリーの森
- にんじんのハート型スライス
包丁が難しい年齢の子には、野菜を手でちぎったり、型抜きで形を変えたりするだけでも大喜び。
また、完成した「アート弁当」や「ベジプレート」は、写真に残して“作品”として記録しておくと、「野菜=たのしい」という記憶として定着します。
2. クイズ大会「野菜博士になろう!」
子どもの知的好奇心をくすぐるのが、野菜に関するクイズです。
こんな問題を出してみてください
- 「ピーマンの中にある白い部分、あれはなんて名前?」
- 「トマトって野菜?果物?」
- 「きゅうりの水分は何%ある?」
クイズはただの遊びではなく、「知ることで好きになる」きっかけになります。
家族でチームを作って競うとさらに盛り上がりますよ!
3. おうち菜園の収穫祭!
夏の間に育てたミニトマトやピーマン、バジルなどがあるご家庭は、収穫そのものがイベントになります。
「自分が育てた野菜を収穫して、料理して、食べる」
——この一連の体験は、子どもにとって「命をいただく」という感覚を自然に教えてくれます。
収穫した野菜を使ってピザトーストを作ったり、サラダを盛り付けたりすれば、ちょっとした“収穫祭”の完成です。

自宅の小さなプランターで育てたミニトマトでも、収穫する喜びは大きいもの。「こんなに赤くなった!」と叫ぶ子どもの声に、親のほうが元気をもらいました。
第3章|野菜嫌い克服に!親子で作れる簡単レシピ
野菜が嫌いなお子さんでも、自分で作った料理なら「食べてみようかな」と思えるもの。親子で一緒にキッチンに立つことで、食への興味も自然と育まれます。
ここでは、手軽にできて、野菜が主役になるレシピを紹介します。
1.にんじんしりしり風たまご炒め
にんじんの自然な甘みと卵のまろやかさが合わさった、野菜デビューにもぴったりの一品。
・にんじん:1本
・卵:2個
・塩:少々
・だし醤油:小さじ1
・ごま油:適量
- にんじんをスライサーで細切りにする。お子さんにはピーラーで皮むきをお願いすると安全で楽しい。
- フライパンにごま油をひき、にんじんを中火で炒める。
- 火が通ったら溶き卵を加え、炒め合わせる。
- 最後にだし醤油を回しかけて完成。
色もきれいで、少し甘みもあるため子どもにも食べやすい一皿です。
2.ナスとチーズのトースター焼き
見た目も味もまるでピザのようなトースターおかず。ナスが苦手でも、これならぺろり。
・ナス:1本
・ピザ用チーズ:適量
・ケチャップ:適量
・オリーブオイル:少々
- ナスを輪切りにし、10分ほど水にさらしてアクを抜く。
- 水気を拭いてオリーブオイルを塗り、トースターで3分焼く。
- ケチャップとチーズをのせて、さらに3〜5分焼いてできあがり。
ピーマンやトマトを追加してカラフルにすれば、見た目の楽しさも倍増します。
3.ブロッコリーのマヨ焼き
青野菜が苦手な子も、マヨネーズとチーズでぐっと食べやすく。
・ブロッコリー:1/2株
・マヨネーズ:適量
・ピザ用チーズ:適量
- ブロッコリーを小房に分け、塩ゆでするかレンジ加熱で柔らかくしておく。
- 耐熱皿に並べ、マヨネーズとチーズをかけてトースターで焼く(5〜7分目安)。
熱々の香ばしさと濃厚な味で、野菜がごちそうに変わるレシピです。

嫌いなものを食べてくれたとき、「やった!」とガッツポーズしたくなりますよね。嫌いを好きに変える鍵は、“一緒に作ること”にあるのかもしれません。
第4章|「食育」のチャンスは日常の中にある
食育というと、堅苦しく感じるかもしれませんが、本来は「生きる力を育む」ためのごく身近な取り組みです。
とくに親子での生活の中には、野菜の日のようなきっかけ以外にも、自然と食育ができるタイミングがたくさんあります。
買い物で野菜の名前を覚える
スーパーに行ったとき、ただ商品をかごに入れるだけでなく、
「これ、何て名前だっけ?」
「これはどこで育ったんだろう?」
などの声かけをするだけで、子どもの“学びのアンテナ”が立ちます。
たとえば
・「にんじんと大根、見た目は似てるけど味は違うよね」
・「このトマト、北海道産なんだって」
といった会話が、観察力や知識の種になります。
食卓で「色のバランス」を意識する
赤(トマト・にんじん)
緑(ブロッコリー・ピーマン)
黄(とうもろこし・かぼちゃ)
——この3色がそろうと、見た目も栄養バランスも整った食事になります。
「お弁当の中に、信号の色がそろってるかな?」
という声かけで、子ども自身がバランスを考えるようになります。
料理を手伝う「小さな役割」が大きな学びに
幼児期は、ピーラーで皮むきや野菜の並べ替え、小学生なら包丁を使った簡単なカットなど、年齢に応じて役割を与えると、自信と達成感を感じられます。
親にとっては時間がかかってしまうこともありますが、その“余白”が子どもの成長に直結します。

「食育」という言葉を意識せずとも、家での会話や一緒の買い物、料理の準備にこそ、学びの種がたくさんあります。
大事なのは完璧なごはんじゃなくて、そこにある親子の会話や時間なんだと思います。
まとめ|野菜の日を、親子の“記憶”に残る1日にしよう
野菜の日(8月31日)は、単なる記念日ではなく、親子で食と向き合う絶好のタイミングです。
忙しい日々の中で、つい“栄養バランス”や“好き嫌い”といった「やるべきこと」に意識が向きがちですが、この日は「楽しむこと」を第一にしてみてはいかがでしょうか。
野菜を育てる
野菜を選ぶ
野菜を切る
野菜を盛りつける
野菜を食べる
このどれか一つを、親子で“体験”として共有するだけで、子どもの中に「野菜=前向きな記憶」が芽生えます。
食は、いのちをつなぐ営みであり、親子の絆を育てる場でもあります。
野菜の日というきっかけを、家族の思い出に変えてみてください。
きっと数年後、「あの時、トマトの顔を作ったよね」なんて笑い合える、温かい記憶になります。

野菜は、“栄養”でもあり、“色彩”でもあり、“遊び”にもなる。
「食べること=学ぶこと=楽しむこと」だと、子どもと一緒に教えてもらった気がします。
今年の野菜の日、我が家でもまた一つ思い出を重ねたいと思います。
それでは最後まで読んでいただきましてありがとうございました!