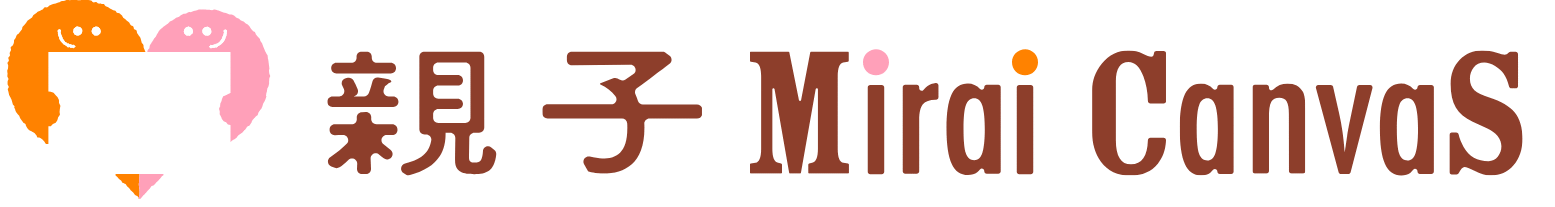みなさんこんにちは!
8月18日は米の日って知ってましたか?
なぜ8月18日が米なの?なにか関係あるの?今日はそんな由来とをお伝えします。
また、私たちの団体が、農家さんを守る田んぼ俱楽部さんとの継続コラボをすることが決定しましたので、詳細をお伝えします!
第1章|米の日の由来
「八・十・八」に隠された意味
米の日は、漢字の「米」を分解すると「八・十・八」になることから、8月18日にちなんで広まった記念日です。
この「八・十・八」という並びは単なる語呂合わせではなく、日本文化における数字の象徴性ともつながります。
古来より「八」は末広がりで縁起の良い数字、「十」は完全・充足を表す数字とされ、それが2つ並ぶ形は豊穣や繁栄を連想させます。
「88の手間」という農業の知恵
お米は田植えから収穫まで多くの工程を経て私たちの食卓に届きます。
「88の手間」という表現は比喩的なものですが、実際には以下のような多岐にわたる作業があります。
- 苗作り
- 田植え
- 水の管理
- 除草・害虫対策
- 台風や大雨への備え
- 収穫・乾燥・精米
この全てを自然の条件に合わせて丁寧に行うため、農家の方々の知識と経験が不可欠です。
記念日の広がりと現代的な意味
米の日は正式な国民の祝日ではありませんが、自治体や農業団体がイベントを開催したり、スーパーが特売やフェアを行ったりすることで認知が広がっています。
特に現代では、米の消費量が減少傾向にある中で、米の日は食文化の再発見と消費拡大のきっかけとしても注目されています。

私は「88の手間」という言葉を知ったとき、お米が“単なる食材”ではなく“文化の結晶”だと感じました。毎日の食卓で「いただきます」と言う習慣も、この背景を知ることでより心を込められるようになります。
第2章|親子で楽しむ米の日の過ごし方
1. 由来クイズで盛り上がる
米の日の朝食や夕食の時間に、「なぜ8月18日が米の日なのか?」と子どもに問いかけてみましょう。
ヒントを少しずつ出して考えてもらうと、知識だけでなく発想力や好奇心も刺激されます。
答えにたどり着いたときの「なるほど!」という瞬間は、親子で共有できる小さな達成感です。
また、「88の手間」について調べてみると、農業の大変さや自然の恵みへの感謝を深く感じられます。
2. 特別メニューを作る
米の日は、お米を主役にした料理を用意してみましょう。
たとえば、家族でおにぎりの具材を持ち寄って「おにぎりパーティー」を開くのも楽しい方法です。
- 定番:梅干し、鮭、昆布
- 変わり種:ツナマヨ、チーズおかか、キムチ納豆
- デザート系:あんこ、きなこ、フルーツ入り
味の好みやアイデアを出し合えば、食卓がクリエイティブな時間になります。
3. 農家さんに思いを馳せる
食卓で「このお米はどこで作られたの?」と話題にするだけでも、食材への意識は変わります。
産地表示を見たり、生産者インタビューを一緒に読んだりすることで、子どもは「食べ物は買うだけではなく作る人がいる」という現実を理解します。
可能であれば、田んぼ見学や農業体験イベントに参加するのもおすすめです。
4. 親子でレシピを記録する
この日に作ったお米料理を写真とレシピ付きで記録し、毎年の米の日に振り返るアルバムを作るのも素敵です。
料理スキルの成長や味の変化が見えて、親子の歴史の一部になります。

母が作ったおにぎりの味って今でも覚えていますよね。米の日は、そんな“時間の贈り物”をくれる日だと思います。
第3章|米の日は食育のチャンス
お米は日本の食文化の中心
お米は単なる主食ではなく、日本の歴史や文化と深く結びついてきました。
稲作は弥生時代から続く農業の基盤であり、祭りや年中行事にも密接に関わっています。
米の日は、こうした背景を親子で知る絶好の機会です。
栄養バランスの話を自然にできる
米の日をきっかけに、食事の栄養バランスについて話してみましょう。
白米は炭水化物の供給源としてエネルギーを与えてくれますが、玄米や雑穀米にすることで食物繊維やビタミンB群、ミネラルも摂取できます。
「どうして玄米は茶色いの?」「雑穀を入れると何が変わるの?」といった質問から、自然と栄養学への興味を育むことができます。
地産地消と環境への関心
産地ごとに異なるお米の品種や味わいを比べてみるのも面白い学びです。
例えば、新潟県のコシヒカリと北海道のゆめぴりかを食べ比べ、香りや食感の違いを話し合うことで、地域性や気候の影響を実感できます。
また、地元産のお米を選ぶことは、輸送によるCO₂排出削減や地域経済への貢献につながることも伝えられます。
「いただきます」と「ごちそうさま」の意味を再確認
食育は単に栄養を学ぶだけでなく、食べ物に感謝する心を育てることでもあります。
米の日に改めて「いただきます」「ごちそうさま」の意味を話し合うことで、子どもは食事が多くの人と自然の力によって成り立っていることを理解できます。

私は子どもの頃、祖母から「ごはん粒を残すと目がつぶれるよ」と言われたことがあります。迷信のようですが、その裏には「一粒一粒に感謝する」という大事な教えがあったと大人になって気づきました。
第4章|田んぼ倶楽部との継続コラボが生む価値
はじめに:コラボの背景
親子Mirai Canvasは、これまでひとり親家庭への食の支援や教育支援、そして子どもたちに体験・学び・遊びのプレゼントをしてきました。
その活動の中で見えてきたのは、「食の確保」だけではなく、食べ物がどう作られているのかを知る体験の重要性です。
一方で、日本の農業は担い手不足や高齢化、消費量の減少という課題に直面しています。
こうした背景から、「支援を受ける家庭」と「支援できる企業・地域」と「農業の現場」をつなぐ取り組みを模索してきました。
そこで出会ったのが、田んぼ倶楽部。
田植えから稲刈りまでをサポートし、企業や個人が“田んぼのオーナー”として関われる仕組みを持つ団体です。
この出会いをきっかけに、米の日をスタートラインとして年間を通じた継続コラボが始まりました。
1. 年間を通じた関わり
今回のコラボは8月18日の米の日をきっかけに始まりますが、活動は単発では終わりません。
田植えから稲刈り、収穫後の発送や食卓での調理まで、年間を通してお米のライフサイクルに関われるのが最大の特徴です。
子どもたちは季節の移ろいとともにお米が育つ様子を目で見て、体で感じられます。
2. 企業のCSRとSDGsの実践
田んぼ倶楽部の「田んぼオーナー制度」を活用することで、企業は次のような社会的価値を生み出せます。
- CSR(企業の社会的責任):ひとり親家庭への食の支援
- SDGs(持続可能な開発目標):特に目標1「子どもの貧困をなくそう」、目標2「100年先の後世に残る「農業、健康、国土」日本の文化文明を次世代へつなぐ。
- ブランド価値の向上:社会貢献を伴う活動は企業の信頼感を高め、採用や顧客ロイヤルティにもプラス
3. 農業体験による教育効果
田植えや稲刈りといった体験は、子どもたちにとって教科書には載らないリアルな学びです。
土の匂い、水の感触、苗の成長など五感を通して農業を体験することで、食べ物の価値や自然との共生意識が育ちます。
また、社員や地域住民が一緒に参加することで、世代や立場を超えた交流も生まれます。
企画しますので、子どもたちを連れて農業体験にいきましょう!
4. 食の循環を“見える化”する
企業が収穫したお米の一部をひとり親家庭に届ける際、「誰が作ったお米なのか」「どんな思いで届けているのか」をメッセージカードや写真で添えることができます。
これにより、単なる物資支援ではなく、“顔の見える支援”として受け取る側の安心感と喜びを高められます。
5. 地域と未来への投資
農業の担い手不足や高齢化は全国的な課題ですが、このコラボは地域農業の活性化にも直結します。
契約や体験イベントを通じて地域農家とつながり、若い世代が農業に興味を持つきっかけにもなります。
100年先まで続く農業文化を守ることは、未来の子どもたちへの最高の贈り物です。
6.オーナー制度の概要
- 企業が田んぼオーナー契約(1区画50kg想定)
- 収穫米のうち一部(例:10〜20kg)を「親子Mirai Canvas」を通じてひとり親家庭に配送
- 残りは従来通り社員・お客様向けに活用
- 配送時には企業名やメッセージカードを同封可能
企業にとってのメリット
・社会課題への直接的な貢献(貧困・食の格差解消)
・社会的価値の創出(CSR・SDGsレポートに掲載可能)
・ブランドイメージ向上(社会貢献を伴う商品・サービスPR)
・社員参加型イベント(田植え・稲刈り体験)
費用とスケジュール
・田んぼ1区画:50kg収穫想定
・料金例:1区画 110,000円(税込・送料込み)
・配送時期:秋収穫後(例:10月〜11月)

オーナーとなった企業様のご厚意で、一部のお米を企業様からご家庭にお届けしていただく仕組みが出来ました。
田んぼ俱楽部様には感謝です!本当にありがとうございます!
第5章|まとめ
米の日は、ただお米を食べるだけの日ではなく、農業文化への感謝と親子の食育を同時に叶えるきっかけになります。
そして今回の田んぼ倶楽部との継続コラボによって、その価値はさらに広がります。
1. 三者にとってのメリット
- 家庭:子どもが自然と食の背景を学び、感謝の気持ちが芽生える
- 企業:CSR・SDGs活動として社会的価値を創出し、ブランド力を高められる
- 農業:担い手不足や消費減少の課題解決に貢献し、地域農業の持続可能性を高める
2. 単発で終わらない「継続性」
多くのイベントや支援活動は一度きりで終わってしまうことがありますが、このコラボは年間を通して続く仕組みです。
田植え、稲刈り、収穫、配送、そして次の季節の準備まで――季節ごとの活動が循環し、関わる人々の関係も深まります。
3. “88の手間”を肌で知る
お米の生産には多くの工程があり、それを「88の手間」と表現します。
その全てを体験や情報を通じて知ることで、子どもも大人も「食べることは生きること」という実感を得られます。
4. 未来へのバトン
この取り組みは、今だけでなく次世代のための投資でもあります。
農業体験を通じて子どもが農業に興味を持ち、将来の担い手や地域の支え手になる可能性もあります。
また、支援を受けた家庭の子どもが大人になって恩返しをする――そんな“支援の循環”が生まれるかもしれません。

私は、このコラボが「米の日」だけの話ではなく、未来の地域や子どもたちの姿までつながっていると感じます。お米一粒に込められた物語を、ぜひ一緒に次の世代へ渡していきたいです。